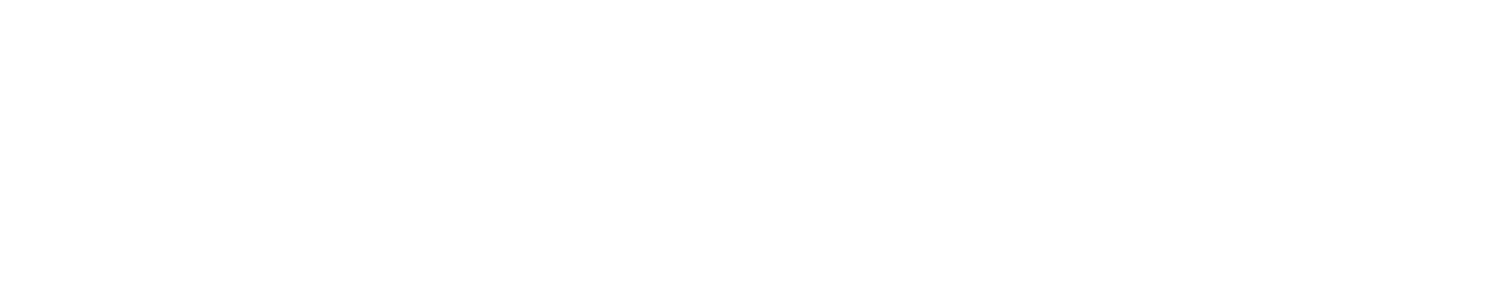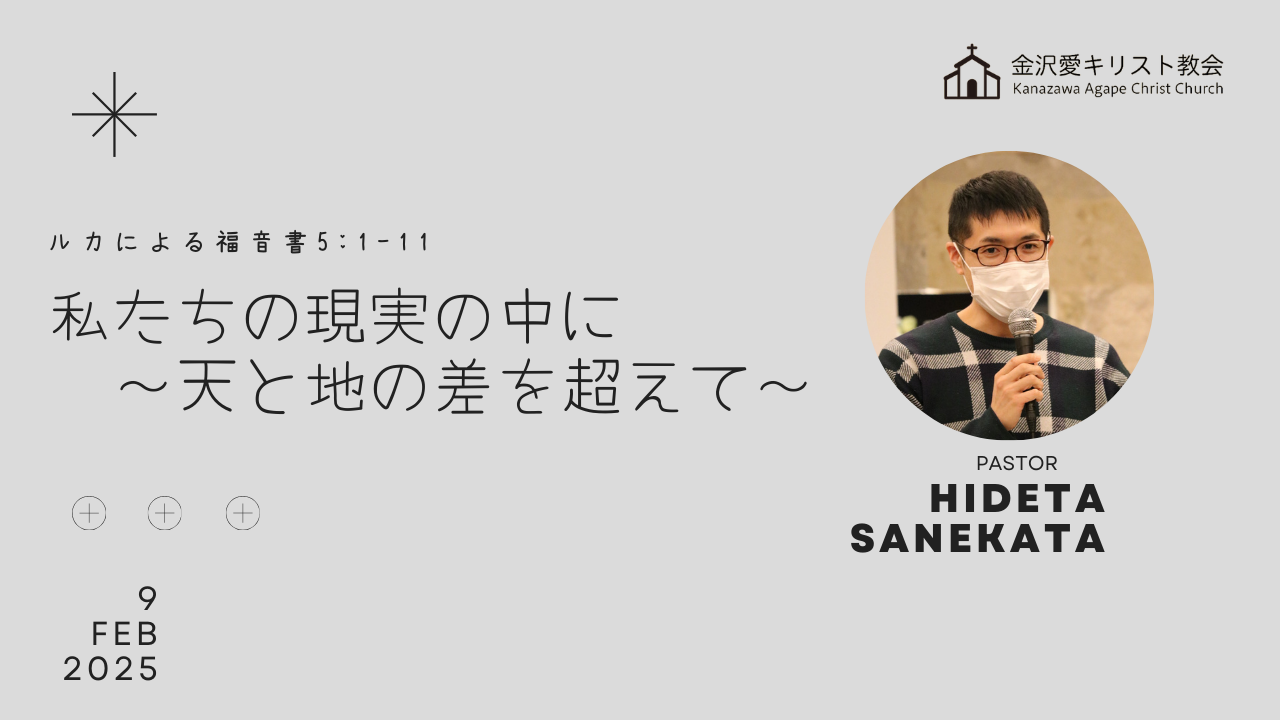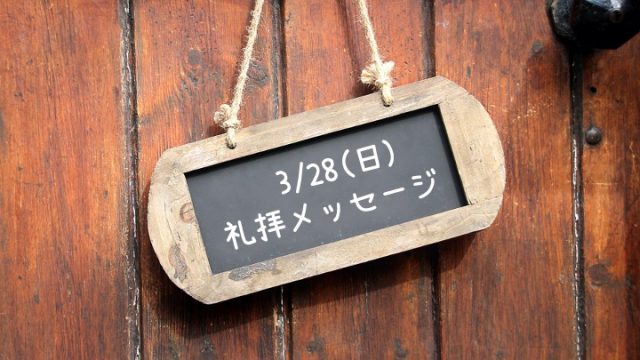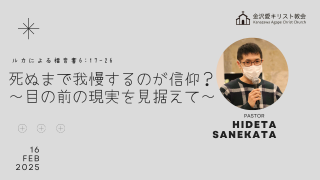大漁の奇跡
今日は、イエスがゲネサレト湖畔(=ガリラヤ湖)にやってきた時の話です。
イエスはそこで、漁師として働いていた人々をご自身の弟子として召し出されたました。
この中にいたのが、十二弟子の一人となるペトロであり、またヤコブやヨハネたちで、彼らはもともと漁師として働いていました。
ペトロたちがイエスから弟子として招かれる話は、マタイやマルコが書いた福音書にも出てくる有名な場面です。
ただ、ルカだけは他の福音書とは少し違って、大漁の奇跡の話を同時に記しています。
この話の中で、ルカは、弟子の中でも特に、ペトロに焦点を当てて書いているように見えます。
ルカは大漁の奇跡の話を通して、ペトロがどのように変化し、イエスに従うようになったのかということを描こうとしているのだと思います。
その日、イエスがガリラヤ湖にやって来ると、岸にある二そうの舟のうち、ペトロの舟に乗り込みました。
そして、岸から少し漕ぎ出してから、舟の上から岸に集まっていた群衆に教え始めました。
この時、ペトロたちはイエスと一緒に舟に乗っていたので、一番近くでイエスの話を聞くことになりました。
ただ、この時ペトロたちは夜通し漁をした後でした。
しかも、何の収穫もなく、心身ともに疲れていたことでしょう。
たぶん「早く家に帰って休みたい」と思いながら、舟の中にいたかもしれません。
イエスの話が全て終わった後、最後に個人的にペトロに話しかけられました。
その言葉は「沖に漕ぎ出して網を降ろし、漁をしなさい」というものでした。
この言葉を聞いて、ペトロはもっとがっかりしたと思います。
なぜなら、その日はもう一晩中、漁をした後だったからです。
漁においては、イエスは素人であり、プロの漁師であったペトロは「先生、わたしたちは、夜通し苦労しましたが、何もとれませんでした」と返しました。
普段、ガリラヤ湖で漁師として働いていた人々は、夜中に漁を行ったそうです。
その日は、漁師たちはすでに漁を終えた後で、しかもペトロたちは網を洗っていたところでした。
もし、また漁に行くとしたら、せっかく洗った網をまた使うことにもなります。
でも、ペトロはイエスに借りがあったようです。
ルカの福音書の4章に書かれていますが、ペトロのしゅうとめが高熱で苦しんでいた時、イエスが家来てくれて、癒してくれたことがありました。
家にまで来てくれるということは、個人的な関わりがあったということでしょう。
それで、はじめペトロは「しかし、お言葉ですから、網を降ろしてみましょう」と言って、イエスの言葉に従い、網を降ろしました。
そうすると、網が破れそうなほどに、たくさんの魚がかかりました。
岸にいた別の漁師に頼んで、もう一舟にも魚を載せても、それでも、舟が沈みそうになるほど多くの魚が取れました。
そうするとペトロは、イエスの足元にひれ伏して「主よ、わたしから離れてください。わたしは罪深い者なのです」と言いました。
普通だったら「いやあイエス様、すごいですね。こんなに取れちゃいましたよ。びっくりですね。」みたいな感じで反応すると思います。
しかし、ペトロはイエスの前にひれ伏し、「私は罪深い者なのです」と告白したのです。
自分の罪深さを感じる時
なぜペトロは突然、自分の罪深さを感じたのでしょうか?
大漁の奇跡の出来事を通して、変化したことの一つが、イエスに対する呼び方です。
5節を見ると、ペトロははじめ、イエスのことを「先生」と呼んでいます。
イエスが舟の上から岸に集まってきた人々に教えていたように、ペトロはイエスをユダヤ教の先生と認識していました。
でも、大漁の奇跡の後には「主よ」というふうに呼び方が変わっています。
これは、ペトロのイエスに対する見方が変わったことを示しています。
先生というのは、あくまでもユダヤ教の教師として尊敬を込めた呼び方です。
それに対して「主」というのは、メシアに対する呼称です。
つまり、ペトロは大漁の奇跡を通して、イエスがメシアであることを悟ったのです。
イエスがメシアであるというペトロの信仰が見て取れます。
さらに、ここで注目したいことは、ペトロがイエスがメシアであると悟った時に、最初に感じたことが、自分の罪深さだったということです。
大漁の喜びやイエスに対する感謝ではなく、自分の罪深さを感じたのです。
これはペトロだけではなく、8節を見ると、一緒に舟にいたヤコブやヨハネも同じだったようです。
彼らの反応は、当時のユダヤ人が、メシアをどういう存在として見ていたのかを明らかにしています。
ユダヤ人たちは、神様がユダヤにメシアを与えてくれると信じていました。
そういう意味で、ユダヤ人にとって、メシアというのは簡単には近づけない存在だった。
ペトロが自分の罪深さを感じたように、メシアというのはとても清く、天と地の差を感じるような存在でした。
それでペトロも、メシアの前に突然ひれ伏して「私は罪深い者なのです」と告白したのだと思います。
現実の中にいるメシア
しかし、イエスはペトロがイメージするようなメシアではありませんでした。
イエスはペトロに「恐れることはない」と言われました。
ペトロはイエスに「わたしから離れてください」と言いましたが、イエス様はそんなこと思う必要はないよと言ってくださったのです。
イエスは清すぎて近寄りがたいメシア、人間と遠く離れているメシアではありませんでした。
その後に、ペトロを「今から後、あなたは人間をとる漁師になる」とイエスに招かれたように、招いてくださるメシアでした。
イエスはメシアとして、遠く離れたところから、私たちをこっちに来なさいと招いたのではありません。
イエスは、私たちの方に自ら来てくださいました。
もちろん、当時のユダヤ人たちが抱いたメシアに対するイメージは、完全に間違っていたわけではないと思います。
確かに、メシアというのは私たち人間からしたら、私たちを超越しているお方です。
簡単には近づけないほど、聖さという面では天と地の差があります。
でも、単に超越していて、近づけない存在ではないということを、イエスの姿が示しています。
超越性がありながらも、同時に内在性があるのがメシアです。
私たちの中にいる、私たちと共にいる、インマヌエルの神様がメシアなのです。
イエスは遠く離れたところから、私たちを見守っているのではありません。
2000年前、イエスがユダヤに生まれ、ユダヤ人として生きたように、私たちの現実の中に来てくださるのがイエスです。
私たちと共に喜び、共に苦しみ、この地の現実の中を生きてくださるお方がおられます。