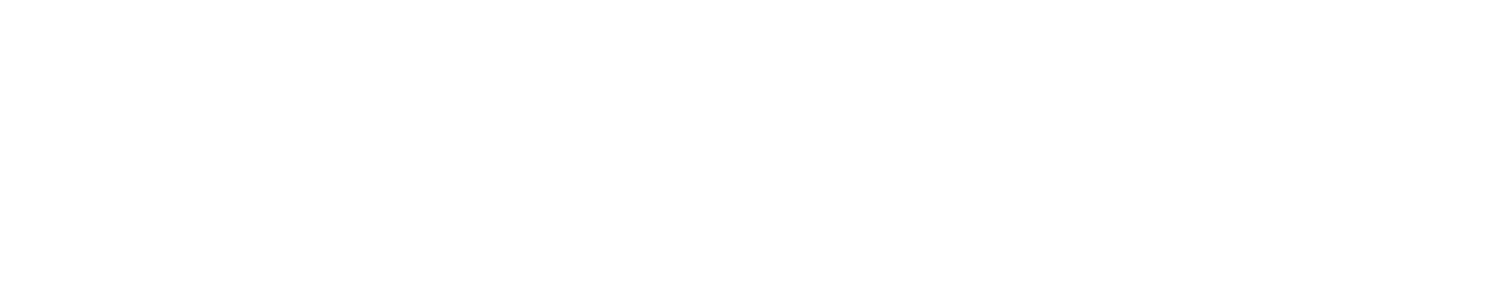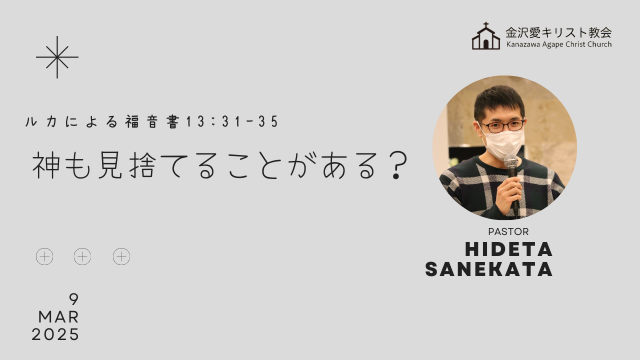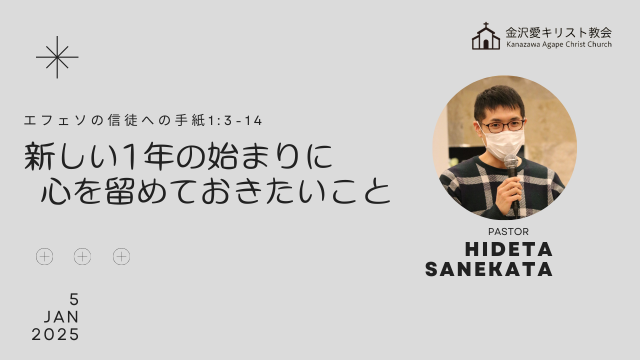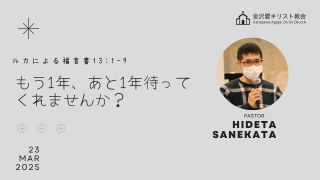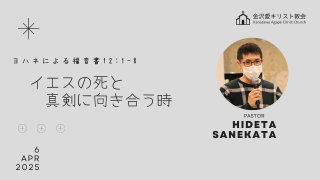父親から遠く離れていた息子
今読んだところは「放蕩息子のたとえ」というタイトルが付けられているように、自分の好き勝手にやりたい放題やった息子の話です。
放蕩息子と呼ばれているのは、二人の息子のうち、弟の方です。
弟は、父親が生きているのに、将来、自分が相続することになっている財産を前もって貰おうとしました。
今だったら、生前贈与ということもありますが、当時のユダヤ社会では、それは慣例に逆らうことでした。
生きているうちに父親に財産を要求することは、父親を侮辱(insult)する行為でした。
このことから、父親とこの息子の関係性が見えてきます。
二人は同じ屋根の下で、家族として暮らしてはいました。
でも、息子の心は父親から遠く離れていました。
息子にとって、父親はいてもいなくてもどうでもいい存在だったということです。
その後、息子は、財産を全てお金に変えて、遠い国に行き、全てのお金を使い果たすまで、放蕩の限りを尽くしました。
お金を使い果たした時、その地方でひどい飢饉が起こったので、食べることもできなくなってしまい、豚の世話をするようになりましたが、それでも食べ物を得ることはできませんでした。
ここまでが、話の前半部分です。
このたとえ話の中で、父親と息子というのは、それぞれ誰のことでしょうか?
父親は神様のことで、息子は神様から遠く離れていた人間のことを指しています。
この息子のように、神様から遠く離れてしまったのが、アダム以降の人間と神様との関係性です。
聖書はこの状態のことを「罪」だと言っています。
罪というと日本語だと「犯罪」のことを意味しますが、聖書で罪という時は、必ずしも道徳的に悪いことだけを指して使われるわけではありません。
この息子は父親から前もってもらった財産で散財しましたが、ここで大切なことは、父親と息子の関係性です。
実は、この放蕩息子のたとえの前に、他に2つのたとえが出てきます。
それが「見失った羊のたとえ」と「無くした銀貨のたとえ」です。
見失った羊のたとえというのは、100匹の羊のオーナーがいて、100匹のうち1匹でもいなくなったら、その1匹を見つけるまで探し回るという話です。
また、無くした銀貨というのは、銀貨を10枚もっている人がいて、そのうちの1枚を無くしたとすれば、見つかるまで探すという話です。
この2つのたとえの中で、いなくなった羊と無くした銀貨というのは、別に何か悪いことをしたわけではありません。
主人のもとから離れてしまっただけです。
このように、人間がもともといたところ、つまり、神様から離れてしまった状態のことを聖書では罪と言っています。
罪というのは、神様との関係性の話なのです。
そのままの姿で帰ってきた息子を迎えた父
たとえ話に戻ると、息子の心は一緒に住んでいる時から父親から遠く離れていましたが、父親はどうだったのでしょうか?
この話の中で一つ不思議なことは、父親が息子から財産を要求された時に、言われた通りに財産をあげたことです。
ユダヤ社会では、父親は家族の中では絶対的な存在です。
律法によれば、両親に反抗的な息子は、石打ちの刑に処すことが許されていたほどです。
しかし、父親は息子を戒めるどころか、ありえない要求をそのまま受け入れたのです。
この父親の姿は、神様と重なるところがあります。
神様というのは、基本的に人間がやることを尊重してくださるお方です。
私たち人間には自由な意思が与えられているが、神様は私たちを支配したりコントロールしたりするのではなく、私たちの意思を尊重しておられます。
またもう一つ、息子のしたことからわかることは、私たちが自分の思い通りにできたからと言って、それが必ずしも幸せにつながるとは限らないということです。
神様は私たちの思いを尊重してくれるので、私たちは何を選んでも自由だが、自由だからこそ、難しいのが人生です。
たとえの後半の話です。
全ての財産を使い果たして、食べることもできなくなってしまった時に、息子は我に返りました。
「我に返った」とき、息子は自分の本当の姿に気づいたのです。
これまで自分が父親のもとにいた時のことを思い返しました。
自分は父親のもとで、どれだけ豊かに暮らしていたのか、父親に対してどういう態度を取っていたのか。
息子は自分の姿を見ながら「私は罪を犯しました」と告白しました。
これは、単に悪いことをいっぱいしてきましたということではなく、父親のことを無視して生きてきましたという告白です。
そして、父親のもとに戻る決心をしました。
でも、普通であれば、簡単には戻れないでしょう。
父親を無視しして生きてきたけど、自分の思い通りにならなかったので、また父親のもとに戻ろうというのは、あまりにも都合が良過ぎる話です。
普通、家に戻るとしたら、せめて自分でもう一度生活を立て直してから行こうと考えると思います。
ちゃんとした仕事に就いたり、父親からもらった分のお金を稼いだりしてから、まともな姿になってから戻ろうと考えるでしょう。
でも、息子は最後まで自分勝手な理由で、父親のもとに戻っていきました。
それにもかかわらず、父親は帰ってきた息子を見つけると、遠くから息子の方へと走り寄り、キスをして迎えました。
そして「死んでいた息子が生き返った」と喜びながら、祝宴を開いたのです。
放蕩する父
これが「放蕩息子」の物語です。
本当は、その後に兄の話がもう少し続くが、今日はここまで見ることにします。
この話の中で、息子以上に放蕩している存在がいます。
ティモシー・ケラーというアメリカの牧師がいますが、彼が書いた本の中に「放蕩する神」というものがあります。
この本の中で、ティモシー・ケラーは放蕩しているのは、実は息子ではなく、神様の方だと言っています。
確かに、息子は、父親が死んだ後に自分が受け取るはずの財産を、まだ父が生きているのに受け取りました。
さらに、受け取った全財産をお金に変えて、遠い国に旅立ち、放蕩の限りを尽くしました。
ただ、そんな息子を何の条件もなく、受け入れた父親こそ、最大の放蕩者だとティモシー・ケラーは言っています。
先週、実のならないいちじくの木のたとえ話を分かち合いました。
3年間、実がならなかったので、ぶどう園のオーナーが、その木を切り倒してしまえと言うが、管理人はもう1年、あと1年待ってくださいと、オーナーを説得します。
この管理人の姿は、神様の姿だと話しました。
放蕩息子に対する父親の姿も同じだと思います。
父親は、息子の帰りを日々、待っていたでしょう。
今年1年も帰って来なかったとしたら、来年こそ帰ってくるはずだ、もう1年、あと1年待ってみようと、息子が帰ってくるまで、父親はずっと待ち続けていたはずです。
神様と私たちの関係というのは変わりません。
私たちにとって神様はいつでも父であり、神様にとって、私たちはいつまでも子供です。
息子がお金も使い果たし、ボロボロになった姿で戻ったように、私たちも今の私のままでいいのです。
もっと立派な姿になって戻ろうと考える必要はありません。
父親はそのままの姿で帰ってきた息子を喜び迎えたのです。
そのように、神様はそのままの私たちをいつでも子供として、受け入れてくださいます。
だから私たちは、神様に対して自分を飾る必要はありません。
今のそのままの姿を神様は愛し、大切に思ってくださるのです。