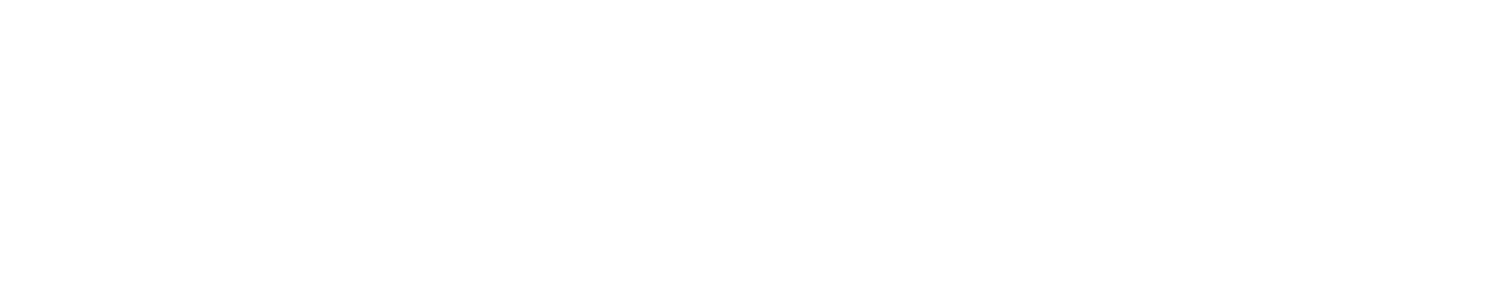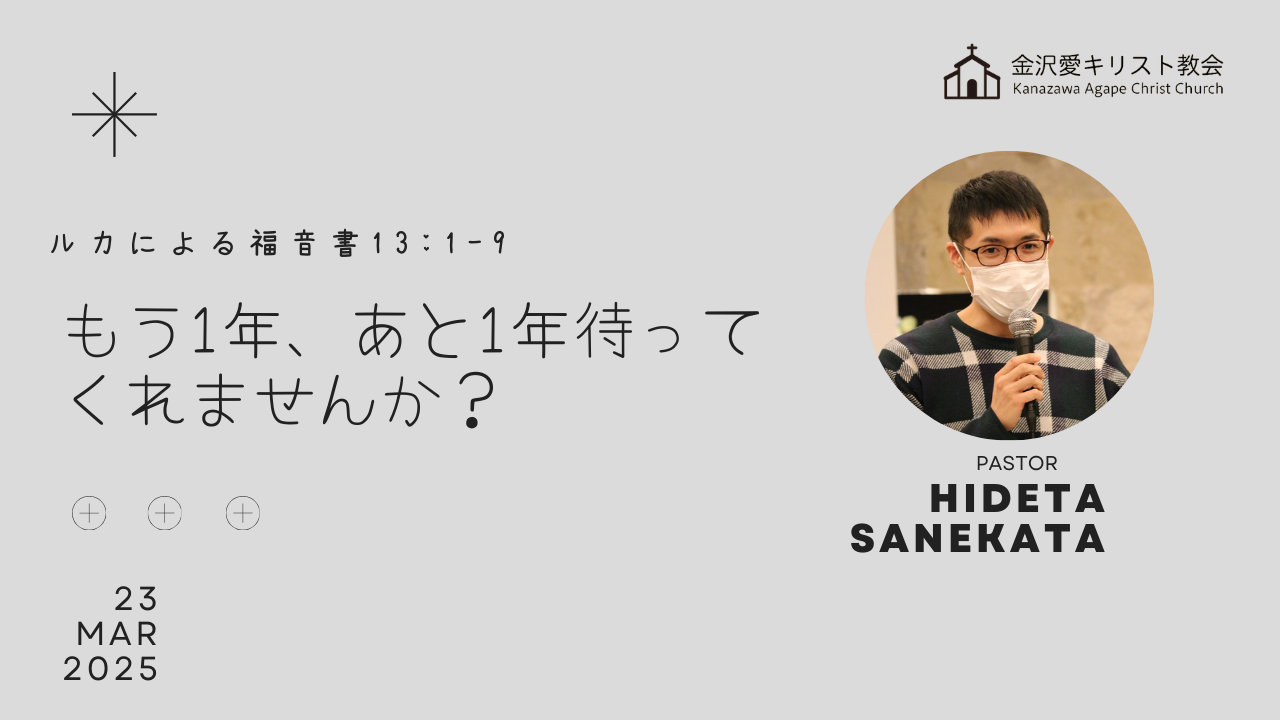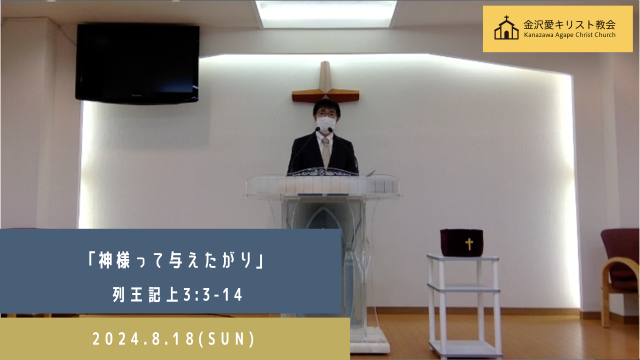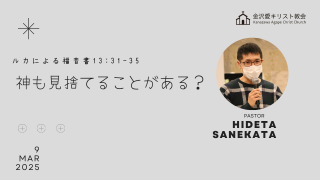罪のせいなのか?
今読んだ中で、少し怖いと思える言葉がありました。
それが3節と5節で繰り返されている「言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる」というイエスの言葉です。
「悔い改めなければ、皆同じように滅びる」という言葉だけを聞くと、なんだか脅されているような感じもします。
首元にナイフを突きつけられて「お前は悔い改めるのか、悔い改めないのか? イエスを信じないなら、地獄に行くぞ」みたいに。
「悔い改めなければ、皆同じように滅びる」というこの言葉だけを聞くと、そういうふうに感じるかもしれませんが、もちろん、神様は私たちを脅迫する方ではありません。
イエスの生涯を見ても、出会った人々に「お前たち悔い改めないと地獄にぶちこむぞ」と言いながら宣教したわけではありません。
こういう強迫観念みたいなものは、キリスト教とは正反対のものです。
もし日曜の礼拝をサボったら「バチが当たる」とか、祈らないと神様から祝福されないという考えがあるとしたら、それは聖書とは正反対の考えです。
それでは「悔い改めなければ、皆同じように滅びる」という言葉の真意はどこにあるのでしょうか?
1節を見ると、この言葉を引き出したのは、ある人々がイエス様のところに来て「ピラトがガリラヤ人の血を彼らのいけにえに混ぜた」とイエスに告げたことにあります。
ピラトというのは、当時、ユダヤを支配していたローマの総督のことです。
ユダヤにはローマに反逆する勢力があって、ガリラヤ人の中にもそういう人々がいたようです。
それである時、ピラトがローマに反逆するガリラヤ人を処刑する事件が起こりました。
それが「ピラトがガリラヤ人の血を彼らのいけにえに混ぜた」という言葉の意味です。
この事件について、イエスはどのように考えていたのでしょうか?
2節でイエスはこう答えています。
「彼らがそういう災難に遭ったのは、他のガリラヤ人たちよりも罪深い者だったからだと思うのか」
イエスは「処刑されたのは、彼らの罪のせいなのか?」という問いかけました。
この問いに対して、イエスは「決してそうではない」と言いながら「あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる」と言われました。
また、当時起こったもう一つの事件について、イエスは語られました。
4節「シロアムの塔が倒れて死んだあの十八人は、エルサレムに住んでいたほかのどの人々よりも、罪深い者だったと思うのか。」
ある時、エルサレムのシロアムというところにある塔が倒れて、18人の人々が死んでしまう事故があったようです。
この事故についても、イエスは「罪が原因だと思うのか」と問いかけました。
そして「決して、そうではない」と言いながら「あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる」と言われたのです。
災いと罪の関係
当時のユダヤでは、罪と災難が深く結びつけられていました。
当時の人々の考えをよく表しているのが、ヨハネによる福音書の9章のある出来事です。
ある時、弟子たちがイエスと歩いていると、生まれつき目が見えない人を見かけました。
それで弟子たちは、イエスに聞きました。
「この人が生まれつき目が見えないのは、だれが罪を犯したからですか。本人ですか。それとも、両親ですか。」と。
このように当時、障害や病気は罪と結びつけて考えられていました。
また、旧約聖書にも同じような話があります。
ヨブ記という書物をみると、ヨブという人にいろんな災難が襲ったとき、ヨブの友人たちがやってきて「それは自分の罪が原因だ」と言って、ヨブのことを責めました。
そして、罪を悔い改めるように説得するのです。
これも、罪と災いを結びつけていたことを示す話だと言えるでしょう。
何もこれはユダヤだけの話ではありません。
日本にも「バチが当たる」という言葉がありますが、これは何か悪いことをした対価に、それ相応の報いがあるということです。
よく子供の本を見ていると、そういう話が多く出てきます。
悪者が出てきて、悪いことをしたことに対して、罰が与えられる。
モラルを教えるためではありますが、そこには赦しや和解というものはほぼありません。
また、日本は自然災害が多い国で、何か大きな災害が起こると、そこに何か神様のメッセージを見出そうとする場合があります。
2011年の東日本大震災が起こった時も、これは偶像崇拝の罪の結果であるとか、悔い改めのチャンスだと考える人もいたようです。
こういう因果応報とか勧善懲悪的な考えは、時代や場所に関係なく、少なからず私たちの中にあるものだと言えます。
それは、これまでにそういうストーリーに数多く接してきたということが深く関係していると思いますが、それ以外の理由として考えられるのは、罪のせいだと考えた方が理解しやすい、納得しやすいということにあると思います。
何か災難が起こった時、「なんでこんなことになるんだ」と考えるよりも、罪が原因だとした方が合理的で分かりやすいのです。
原因があって、今の結果があるというように現実を受け止めようとする一つの反応だと言えるでしょう。
オーナーを説得する管理人
こういう考えを、イエスの言葉に当てはめると、悔い改めない(=罪)と滅びる(=罰)ということになります。
しかし、イエスは罪と罰の概念自体を変えられました。
イエスの言動からは「罪があるからあなたたちはダメだ」とか「罪を犯した責任はあなたたちにある」というメッセージは出てきません。
イエスは、そうやって私たちを責め立て、責任を追求するのではなく、自らその罪を背負い、その対価を払ってくださいました。
イエスが願っていることは、ただ私たちが悔い改めることではありません。
私たちが神に依り頼むということです。
その中に、悔い改めがあるのです。
この悔い改めについて、イエスは6節から「実のならないいちじくの木のたとえ」を通して語っています。
ある人(ぶどう園のオーナー)が、自分のぶどう園にいちじくの木を植えました。
その後、いちじくの実を収穫しようとしたが、3年間、全く実がなりませんでした。
それで、ぶどう園のオーナーは、園丁(管理人)に対して、木を切り倒すように言いました。
しかし、管理人は「実がなるようにやってみるので、今年もこのままにしておいてください」と言って、もう1年待ってくれるようにオーナーを説得しました。
このたとえのポイントは、この話の中で、誰が神様なのかということです。
オーナーと管理人、2人の登場人物がいますが、聖書の他の話だと、ぶどう園のオーナが神様のことを指す場合が多くあります。
ただ、このたとえの中では、神様は管理人の方です。
ぶどう園のオーナーに対して「もう一年待ってください」と頼み込んだ管理人こそが、神様の姿です。
神様に依り頼みながら
このたとえの中で、実がなるということが、悔い改めるの実を結ぶということでしょう。
つまり、実がならないというのは、悔い改めの実がないということです。
悔い改めの実がない時に、その木を切り倒してしまえと言うのは誰でしょうか?
それは、人間であり、サタンもそのように考えるでしょう。
しかし、少なくとも神様はそのようには言われません。
管理人が「今年もこのままにしておいてください」と言っているように、神様は、今年悔い改めの実がなかったなら、もう1年待ってくださいと言われます。
ここで管理人は「来年、実がならなければ木を切り倒してください」と言っていますが、もしまた来年、実がならなかったとしたら「もう1年待ってください」と神様は主人にお願いしてくださるでしょう。
このように、神様は私たちに対して「悔い改めなければ滅ぼすぞ」と言われるのではなく、もう1年、あと1年と待ってくださるお方です。
神様の願いは、一人も滅びることがないように、皆が悔い改めて、神様と共に生きていくことにあります。
ここで悔い改めというのは、単に自分の罪を後悔することではない。
「もう同じことはしない」と、決心することでもありません。
悔い改めという言葉には、向きを変えるという意味があります。
私たちは、自分の罪深さばかりを考えて、自らの情けなさを嘆くのではなく、神様の方に向き直す必要があるのです。
つまり、こんな自分でも愛してくださる、赦してくださる神様の方を向くことです。
そのように、神様からの赦しの中で生きていくことが、悔い改めた人の人生です。
周りからは責められることがあるかもしれません。
自分で自分を責めることもあるかもしれません。
でも、神様は私たちを責めたり、脅したりする方ではありません。
神様は私たちのことをいつまでも待ってくださるお方なのです。