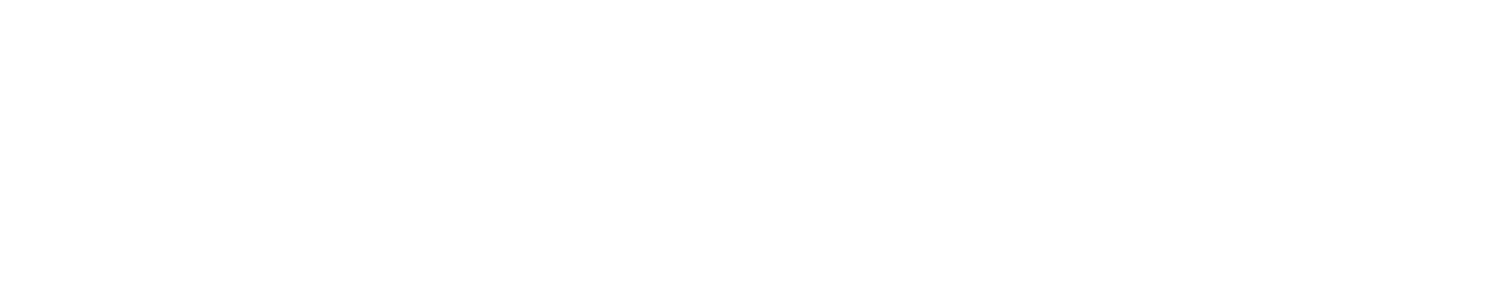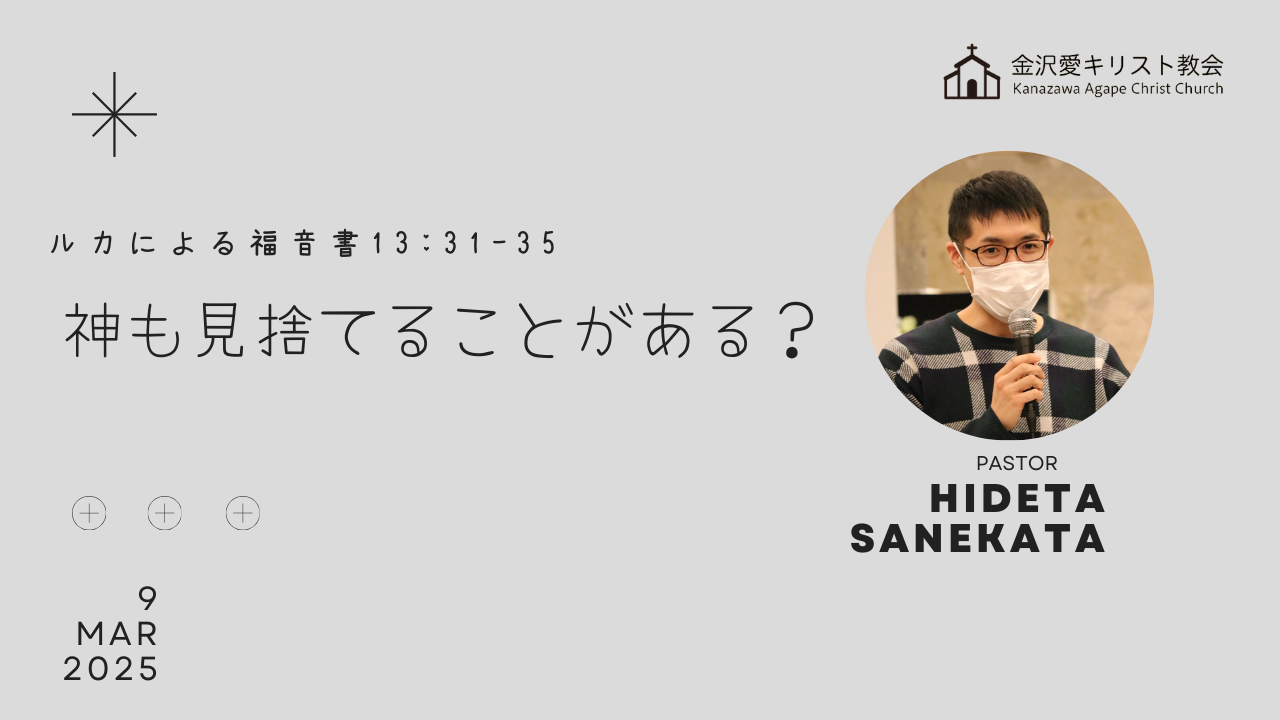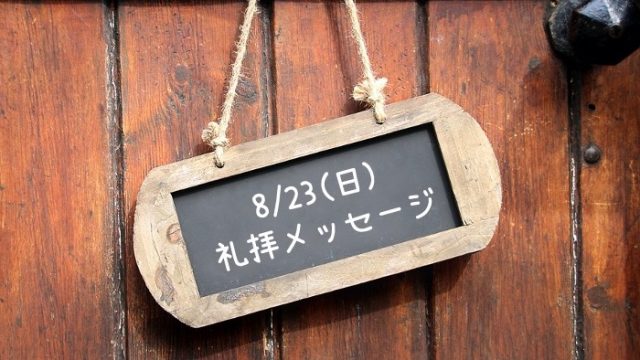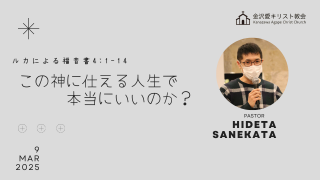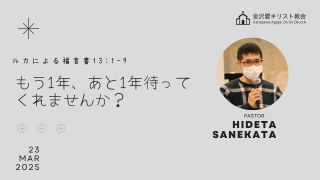エルサレムに向かうイエス
今日はイエスが受けた苦難を覚える四旬節(レント)の第2週目の日曜日です。
今読んだところは、イエスがファリサイ派の人々に対して語ったことが書かれていますが、読んでみてわかるように、イエスはかなり厳しい言葉を使いながら語っています。
聖書によっては、ところどころにサブタイトルが付いているものがありますが、今日の箇所は新共同訳の聖書には「エルサレムのために嘆く」というサブタイトルがついています。
そのように、この聖書箇所は、エルサレムに対するイエスの嘆きです。
エルサレムは、世界で最も古い都市の一つと言われている歴史ある町です。
聖書の中では、エルサレムというと、イスラエルを象徴する場所だと言えます。
旧約時代、ユダ王国の首都がエルサレムであり、そこに神殿が建てられました。
新約聖書では、イエスが最後、十字架で殺された場所がエルサレムでした。
このエルサレムという言葉には「平和の町」という意味がありますが、今日の場面でイエスが語っていることを聞くと、平和という雰囲気はありません。
33節の最後を見ると「預言者がエルサレム以外の所で死ぬことは、ありえないからだ」とあります。
この場合、預言者というのは、イエス自身のことで、イエスは「私は必ずエルサレムで死ぬ」と語っています。
また、34節では「エルサレム、エルサレム」と呼びかけながら、語っています。
ここでは「預言者を殺し、人々を石で打ち殺す者よ」と、イエスはエルサレムのことを嘆いています。
この場合、預言者というのは、これまで神様がメッセージを伝えるためにイスラエルに送った人々のことです。
これまでイスラエルに現れた預言者たちは、殺された者も多かったようです。
このように、歴史的にエルサレムという場所は、多くの血が流されてきたところです。
それでは、イエスにとってエルサレムとはどういう場所だったでしょうか?
この時、イエスが目指していたところは、エルサレムでした。
この地上において、イエスの最終目的地が、エルサレムです。
イエスが言われた「自分の道」というのは、エルサレムへの道です。
この道は、十字架への道、最後には死が待っている道です。
イエスが「預言者がエルサレム以外の所で死ぬことは、ありえないからだ」というように、イエスはエルサレムに行ったら、そこで何が起こるのかをよく知っておられました。
それでも、イエスは自分の道を進んでいかれました。
この「自分の道を進まねばならない」という言葉は「自分の道を進むことになっている」という意味にも取れる言葉です。
「進むことになっている」というのは、初めからそのように決まっているということです。
つまり、そこには神様の計画がありました。
イエスが進んだ自分の道は、父なる神様から与えられた道でした。
イエスには、父なる神様から任された使命がありました。
それがエルサレムへの道、十字架の死に至る道です。
見捨てられた神殿
イエスは、このエルサレムに対して嘆かれました。
イエスは「エルサレム、エルサレム」と呼びかけているが、ここでエルサレムというのは、ユダヤの民を指しています。
ユダヤの民は、神様が遣わした預言者たちの言葉を無視して、神様に逆らい続けてきました。
それでも神様は、めん鳥(親鳥)が雛(子供)を羽の下に集めるように、ユダヤの民を守ろうとしました。
しかし、ユダヤの民は、それに応じようとしませんでした。
自分たちは大丈夫だと、神様のことを拒絶したのです。
父なる神様が送ったイエスに対しても、ユダヤの民は最終的には皆、拒絶しました。
その結果が、十字架です。
そのように、ユダヤの民が血を流し続けてきた結果、何が起こることになるでしょうか?
35節を見ると、イエスは「見よ、お前たちの家は見捨てられる」と言っておられます。
「見捨てられる」というのは、私たちにとって一番怖いことです。
子供にとっては、親に見捨てられることが一番残酷なことです。
神様というと、愛の方であり、最後まで見捨てない方です。
私たちが信じる神様は、見捨てない神様のはずです。
でも、ここでイエスは「見捨てられる」と言っているのです。
神様は本当に見捨ててしまうのか、それとも見捨てないのか、どちらでしょうか?
この場面で、イエスはファリサイ派の人々と話しています。
その中で「お前たちの家は見捨てられる」と言われました。
ここで見捨てられるのは、お前たちの家です。
ファリサイ派などの宗教指導者たちにとって、家というのはどこのことでしょうか?
それは自分が住んでいる家ではなく、神殿のことです。
つまり「お前たちの家は見捨てられる」というのは「神殿は見捨てられる」ということです。
実際に、この時から40年ほど経った時、AD70年に、エルサレムにある神殿はローマ軍によって焼き払われてしまいます。
そして、エルサレムという街全体が、ローマに占領され、エルサレムは破滅することになります。
それでも見捨てられない
このように、イエスはこのエルサレムに対して、ユダヤの民に対して、嘆きました。
「なぜ血を流し続けるんだ?」「なぜ私に逆らい続けるんだ?」と。
イエスはエルサレムのことを嘆きながら、十字架へと進んでいかれました。
イエスの嘆きの言葉を聞くと、エルサレムには何の希望もないように思えます。
神様が送った預言者に逆らい続け、神様の独り子として来られたイエスでさえも、十字架につけて殺してしまいました。
血を流すことによって、全てを解決してきたのが、エルサレムです。
イエスの時も、十字架によってすべてが終わってしまったように思えます。
しかし、十字架の死は終わりではありませんでした。
イエスがファリサイ派の人々に語っている言葉の中に、32節を見ると「三日目にすべてを終える」という言葉があります。
三日目というのは、十字架の死から三日目ということでしょう。
イエスは死んで三日目に復活されました。
死によってすべてが終わったのではなく、復活によって、父なる神様から任された使命を果たされたのがイエスです。
イエスが言った「お前たちの家は見捨てられる」という言葉の中に、実は希望が隠されています。
なぜこの言葉が、希望の言葉なのでしょうか?
それは、見捨てられるのは「お前たち」ではないからです。
もし、イエスが「わたしはもうお前たちを見捨てる」と言われたとしたら、もう本当に終わりでしょう。
でも、見捨てられたのは、お前たちではなく、お前たちの家、神殿です。
神殿は見捨てられたかもしれないけど、お前たち、すなわち、ユダヤの民は見捨てられていないのです。
これまでユダヤの民は神様のことを何度も見捨ててきました。
イエスも、十字架にかけられたということは、見捨てられたということです。
でも、何度見捨てられても、神様は民を見捨てることはありませんでした。
イエスは三日目に復活し、その後、天に昇り、ご自身の霊である聖霊が降されました。
イエスは今、私たちと共に生きてくださっているのです。