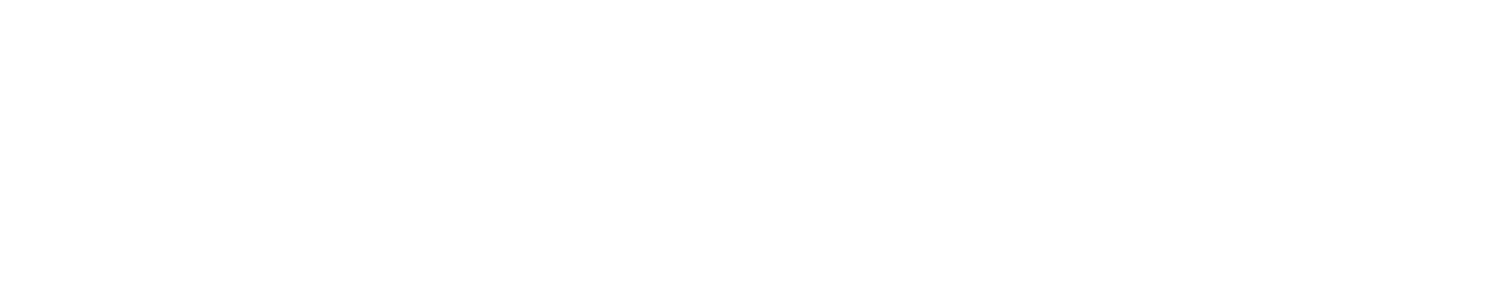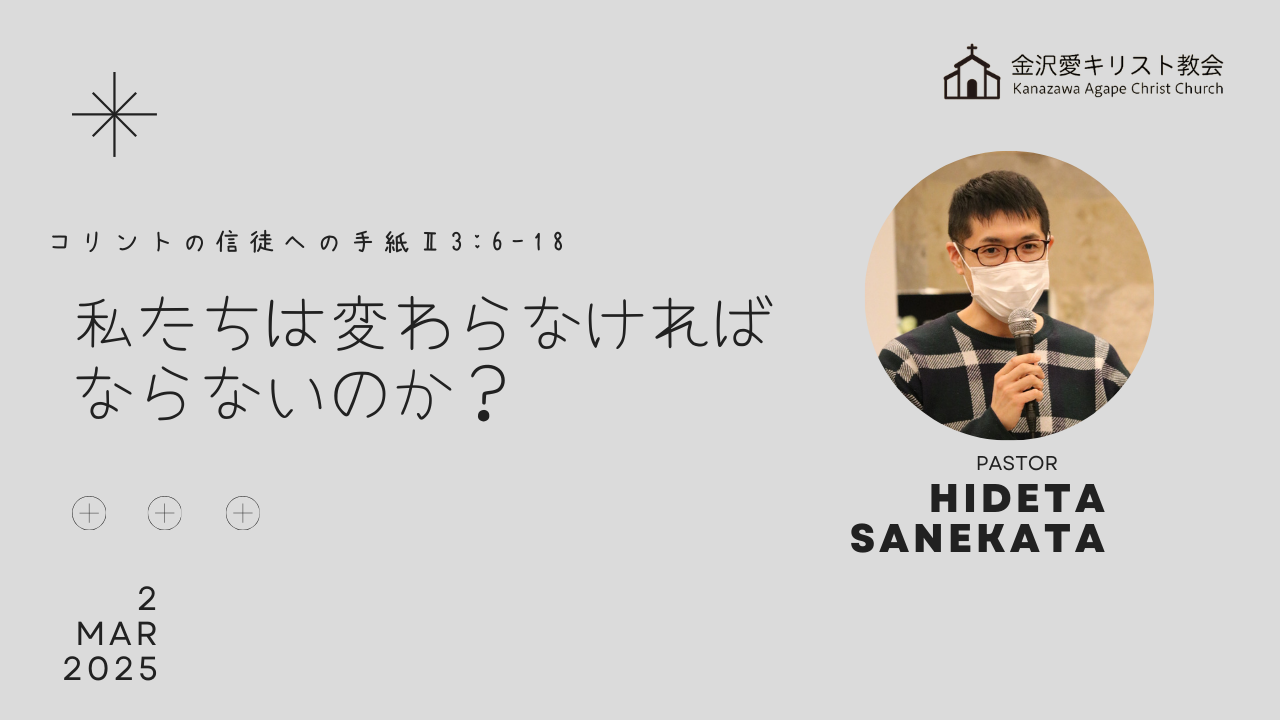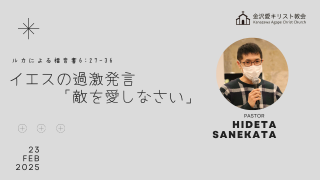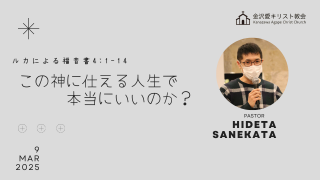今のままでいい?
今日のメッセージのタイトルは「私たちは変わらなければならないのか?」です。
皆さんは、今の自分自身を見ながらどう思うでしょうか?
「私は変わらなければならない」と思うでしょうか?
それとも「今の自分でいい」「このままで大丈夫」と思うでしょうか?
おそらく、多くの人は、人生のどこかで「自分を変えたい」とか「もっと違う自分になりたい」という思いを持ったことがあると思います。
「このままではいけない」「もっと成長しなければならない」と。
また、自分に対してだけではなく、周りの人に対しても変わるべきだという思いを持ったり、今の状況を変えたいと悩んだりもします。
このように「変わりたい」「変えたい」「変えなければならない」という思いが、私たちを奮い立たせてきます。
それでは、神様は私たちを見ながら、何と言われるでしょうか?
「あなたは変わらなければならない」と言われるでしょうか?
それとも「今のままで大丈夫だよ」と言われるでしょうか?
クリスチャンとして信仰を持っている人であっても「今のままではいけない」「変わるべきだ」と考える人はそれなりにいるでしょう。
なぜなら、イエスを信じる人は信じた時点で終わりではなく、そこがスタートラインになるからです。
実際に聖書でも、私たち個人のレベルにおいて言うと、私たちはキリストの似姿へと変えられるとあります。
今日分かち合う箇所の最後、18節に「主と同じ姿に造りかえられていきます」とあります。
聖書は、私たちが聖霊によって、イエスと同じ姿へと変えられていくと語っています。
信じた時点で完全に変えられるのではなく、信じた時点から徐々に変えられていくということです。
こういうことを根拠に、クリスチャンの中にも「今のままではいけない」という思いを持つ人もいるでしょう。
無条件の愛?
確かに「変わらなければならない、変わりたい」という思いは、とても真剣で、切実な願いだと思う。
ただ、神様は私たちに向かって「今のままではいけない」「もっと成長しなければならない」と、私たちを責めてくるような方ではありません。
よく、神様の愛は「無条件の愛」だと言われます。
私たちが何かの条件を満たして初めて、神様が私たちを愛し、救うのではありません。
こちら側の理由や根拠によらず、ただ信じればよいだけだ、と。
ただ、信仰を持った途端、無条件ではなくってしまうことがあります。
信じるまでは無条件だと言われていたのに、信じてからは、特に教会生活においていろいろな条件が課されるように感じる人もいるでしょう。
むしろ、2000年前のユダヤでそのように人々に接していたのが、ファリサイ派などの宗教指導者たちでした。
彼らは律法を守らない人々に対して「これではいけない、あなたは神から遠く離れている」と教えてい他のです。
律法学者たちは、ただ律法を守るように教えたのではなく、律法を守らない人、守れない人々を罪に定めていました。
しかし、神様は今の私たちを見ながら「このままではダメだよ」と言われるようなお方ではありません。
私たちの全てを知っていながら、私たちをそのままに愛し、受け入れてくれるのが神様です。
その上で、神様は私たちが主と同じ姿に変えられていくと言っているのです。
新しい契約の仲介者イエス
今日の聖書箇所の中に、古い契約と新しい契約が出てきます。
古い契約というのは、神様がモーセを通してイスラエルと結んだ契約です。
神様はモーセの時代に、イスラエルの民をエジプトから導き出し、シナイ山で律法を与えました。
神様は律法を通して、イスラエルの民が神の民としてどう生きるかということを教えようとされました。
特に、律法の中心である十戒(10の教え)は、石の板に刻まれ、イスラエルの民にとって重要な教えとなりました。
しかし、イスラエルの民は律法に背き、神様との契約を破ってしまいました。
律法を軽んじ、神様を軽んじるようになったイスラエルは、ついには、バビロンに占領され、国が滅亡することになりました。
しかし、この出来事は、神様がイスラエルの民を見捨てたことを意味するわけではありません。
国が失われる直前に、神様はエレミヤという預言者を通して「新しい契約」について伝えていました。
モーセを通して結ばれた古い契約では、律法は石の板に刻まれましたが、新しい契約では、律法は民の胸の中に授けられ、心に記されます。
この新しい契約を結ぶために来られたのが、イエス・キリストです。
ヘブライ人への手紙の著者は、イエスのことを「新しい契約の仲介者」だと言っている通りです。
何に仕えるのか?
イエスを通して結ばられる新しい契約によって、明らかになったことがあります。
それは「神様の赦し」です。
今の34節に「わたしは彼らの悪を赦し、再び彼らの罪に心を留めることはない」とあります。
神様はどんな悪であっても赦し、再び罪に心を留めることはないとはっきりと言われました。
何があっても、すでに赦されている、すでに受け入れられているということです。
ただ一つ、ここで勘違いしてはならないことは、イエスは律法を廃止するために来たわけではないということです。
イエス自身「私は律法を廃止するためではなく、完成させるために来た」と言っているように、イエスは律法の完成者です。
ある時イエスが、律法の専門家から「律法の中でどの掟が最も重要か」と聞かれたことがありました。
その時に、イエスは「神様を愛すること」と「隣人を愛すること」だと答えられました。
イエスはその通り、神様を愛し、隣人を愛する人生を生きました。
律法に忠実に生きたのが、イエスです。
主と同じ姿というのは、まさにこの姿のことです。
イエスが神様を愛し、隣人を愛したように、私たちも神様を愛し、隣人を愛する者へと変えられていくのです。
新しい契約に仕えるものへと変えられていくのです。
古い契約というのは、文字に仕えることです。
神様を愛さなければならない、隣人を愛さなければならないと、文字通りに生きようと、文字に仕えて生きていくことです。
しかし、文字は殺します。
文字に仕えて生きていこうとすると、いずれ殺されることになります。
なぜなら、文字は人を罪に定めるからです。
ファリサイ派がやっていたことが、まさにこのことです。
律法の文字を使って、人々を罪に定め、裁いていました。
「この通りにできないあなたはダメだ」「今すぐに変わらなければならない」と言いながら、文字に仕えるように教えていました。
これが、律法主義というものです。
律法主義は、単にルールに手厳しいということではありません。
まず、基準を設定します。
クリスチャンであれば、聖書の真理を元にして、自分なりの目標やルールを定めます。
これを達成できればOK、しかし、それができなければ「このままではダメだ、変わらなければならない」となります。
できない自分を否定するようになっていきます。
文字に仕えよう、仕えようとすると、文字はできない私を罪に定めてきます。
そうすると、私たちは文字に殺されることになります。
霊に仕える人生
しかし、聖書が教えていることは、文字に仕えることではなく、霊に仕えることです。
霊に仕えるというのは少し難しい表現ですが、16節の御言葉によると「主(=霊)の方に向き直ること」だと言えます。
私たちは、文字ばかりを追いかけて、理想だけを追求してもっと立派なクリスチャンになろう、愛がある人になろうと生きるのではありません。
私たちには聖霊が与えられています。
霊が共にいて、霊が導き、霊が変えていってくださることを信じること、これが霊に仕えることです。
私たちは「変わらなければならない」のではなく「霊によって変えられていく」のです。
聖霊の働きによって、主であるイエスと同じ姿に変えられていくのです。
神様を愛し、隣人を愛する者へと変えられていくのがクリスチャンです。
この新しい契約の中で、神様を信じていくことが、信仰です。
だから、もし私たちが「前と少しも変わらない」と思ったとしても大丈夫です。
変わらなければ、変わらなければと、自分にプレッシャーをかける必要はありません。
なぜなら、新しい契約は赦しに基づいているからです。
すでに赦されている、すでに受け入れられているのです。
神様は私たちに対して「あなたは今のままではいけない、変わらなければいけない」とは言いません。
神様は「今のあなたで大丈夫だ」と言ってくださるお方です。
足りないところだらけだと思えたとしても、今の私を肯定してくださるお方です。
もし、変えられる必要があるとしたら、主の霊が私たちを造り変えてくださいます。
私たちの手で、なんでも変えられるとすれば、信仰は必要ありません。
努力と頑張りだけやっていけばいいのです。
でも、変えたくても、変えられないことがあります。
変わろうと思っていなくても、変えられることもあります。
神様の救いというのは、私たちの努力を超えたところにあります。
だからこそ、私たちは信じるのです。
信仰を持って、生きていくのです。