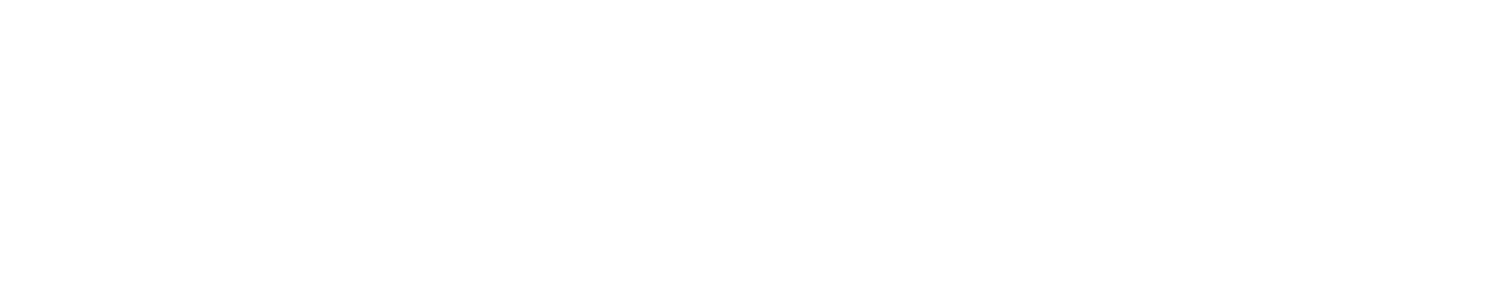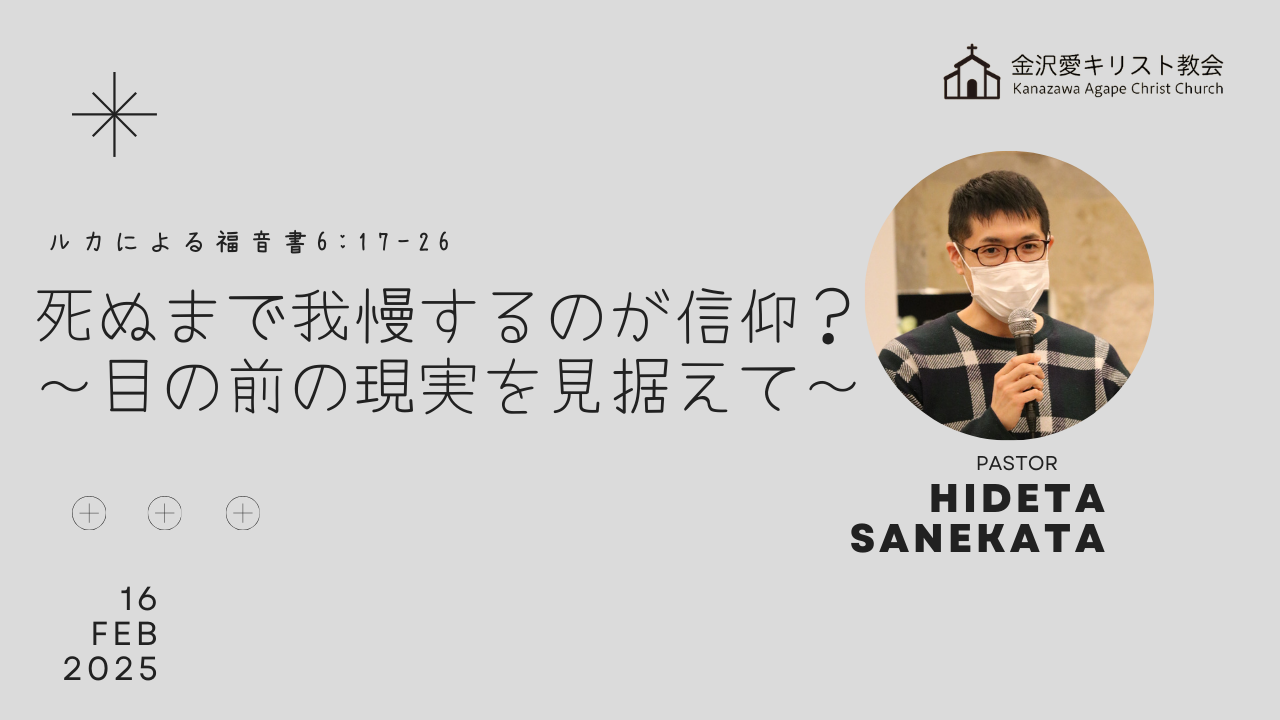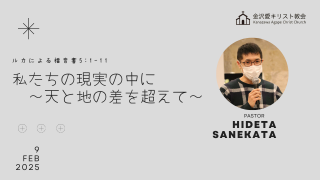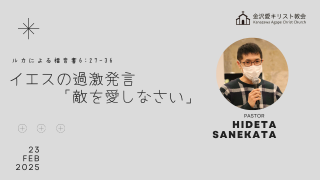イエスに宿る力
イエスがユダヤの社会に登場してから、その噂は一気に広まりました。
ユダヤだけではなく、遠く離れたところからも、イエスに会うためにユダヤを訪れたため、イエスの周りにはいつも人だかりができていました。
それは、イエスの教えを聞くためであり、また、病気や悪霊から癒してもらうためでした。
そして、多くの人々がイエスの弟子となり、イエスについていきました。
先ほど読んだ19節に、少し不思議なことが書かれている。
「群衆は皆、何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出て、すべての人の病気をいやしていたからである。」
人々は皆、なんとかしてイエスに触れようとしました。
そうすれば、病気が癒やされたからです。
「イエスに触れれば癒やされる」というのは、今の私たちが聞いたら、ちょっと引っかかると思います。
迷信のようなことに聞こえるからです。
日本でも、お寺や神社に行くと、何かに触れると癒やされる御神体と言われるものがあります。
そういう類のものと同じように、イエスに触れれば癒やされるというのは、キリスト教的には少し危ない信仰のように感じます。
ただ、聖書の他のところを見ても、イエスに触れて癒やされるということは単なる迷信ではなく、本当に起こっていたことのようです。
福音書の中に、12年間、出血の止まらない女性が出てきます。
この女性も、病の癒しを求めて、イエスのもとにやってきました。
彼女がイエスの服に触れた時、出血がすぐに止まって、病気が癒やされました。
その時、イエスはの内から力が出て行ったことに気づいたと聖書には書かれています。
この話は、病気の女性がイエスに触れたことで、イエスの力によって癒やされたということを表しています。
今日の19節にも「イエスから力が出て、すべての人の病気をいやしていたからである」とあります。
このように、イエスに触れることで、イエスの力によって病気が癒やされるということが起こっていたようです。
ただ、聖書を見る限り、イエスが「私の体に触れなさい、そうすれば癒やされる」と教えているところはありません。
イエスが病気を癒す時に、体に触れて癒すことはありましたが、その時にイエスは「よくなりなさい」とか「見えるようになりなさい」とか、そういう言葉を発しながら人々を癒すことがほとんどでした。
もし、イエス様に触れなければ病気が癒やされないとしたら、どうなるでしょうか?
癒しというものが、イエスが天に昇った後の人々、今の私たちにとっては関係ないことになってしまいます。
2000年前の人だけの、しかもユダヤのあたりに住んでいて、イエスに直接出会うチャンスがあった人だけの話になってしまいます。
だからこそ、イエスは言葉を通して、数多くのことを伝え、教えたのだと思います。
確かに、イエス自体に力があったので、その体に触れることで病は癒やされました。
同様に、イエス自体に力があるのであれば、その口から出た言葉にも力があるのです。
その言葉は時代を超えて、今の私たちのところに届き、働いているのです。
幸いである
今日の20節から最後までが、イエスが残した山上の説教と言われる箇所です。
マタイによる福音書にも出てきて、そちらの方がよく知られています。
マタイの方では8つの祝福が書かれているので、八福の教えと言われていて、教会が昔から大切にしてきたイエスの言葉です。
ルカの方を見ると、8つのうち、前半は「幸いである」いう祝福を伝えていますが、後半は「不幸である」という言葉に変わっています。
これは、前半と後半で言葉を言い換えて、結局はほとんど同じことが繰り返し語られています。
なので、今日は「幸いである」という方の言葉を特に聞いていきたいと思います。
イエスはどのような人が幸いであると語っているのでしょうか?
20節から22節までを見てみると「貧しい人々、飢えている人々、泣いている人々、人に憎まれている人、信仰のゆえに迫害を受けている人々」こういう人々のことを幸いであるとイエスは言っています。
では、なぜそういう人々が幸いであると言えるのでしょうか?
それは飢えている人はいつか満たされるからであり、泣いている人はいつか笑うようになるからです。
また、不幸であるという方の言葉を見てみると、今満腹していても、いつか飢える時がくるのであり、今笑っていても、いつか悲しみ泣く時が来るとイエスは言います。
これだけをみると「人生山あり谷あり、良い時もあれば悪い時もある、だから目の前だけのことを考えるのではなく、頑張りましょう」みたいな、励ましの言葉に聞こえてしまうかもしれません。
でも、もちろん、イエスは単に「人生いろいろあるよね」ということを伝えようとしているのではありません。
注目したいのは、20節と23節にある「神の国」と「天」という言葉です。
ここでイエスが伝えようとしていることは、神の国、天のことです。
確かに、私たちがこの地上で歩む人生にはいろいろあります。
それを踏まえた上で、イエスは私たちの目を天に向けさせています。
私たちの目には、目の前の現実しか見えないことがあり、そこで起こっていることが全てのように感じることがあります。
でも、そうではなく、最終的に私たちには天という希望があるのです。
すでに始まっている神の国
だからと言って、イエスは私たちに「死ぬまで我慢してね」と言っているわけではありません。
「この地上では苦しいことばかりかもしれないけど、天国では幸せに過ごせるから、それまで何とか辛抱してね」という安易な励ましをしているのではありません。
もし、そうだとしたら、イエスは地上に来ることなく、天で待っていればよかったのです。
天の上から、こういうことを伝えればよかっただけです。
しかし、イエスはこの地上にやって来てくださいました。
それは、神の国が近づいたことを知らせるためです。
この地上において、私たちが泣いたり、悲しんだりしている時、イエスもそこで一緒に泣いてくださるのです。
私たちが笑い、喜んでいる時、イエスもそこで一緒に喜んでくださるのです。
そして、これはイエスと私だけの間で完結するものではありません。
教会という共同体の中に広がっていくのです。
最終的には天において実現することが、私たちの中で起こっていくのです。
私たちは天に行って、イエスに出会い、イエス様に触れるまで、我慢する人生を生きているのではありません。
すでに、神の国は私たちの中で始まっているのです。